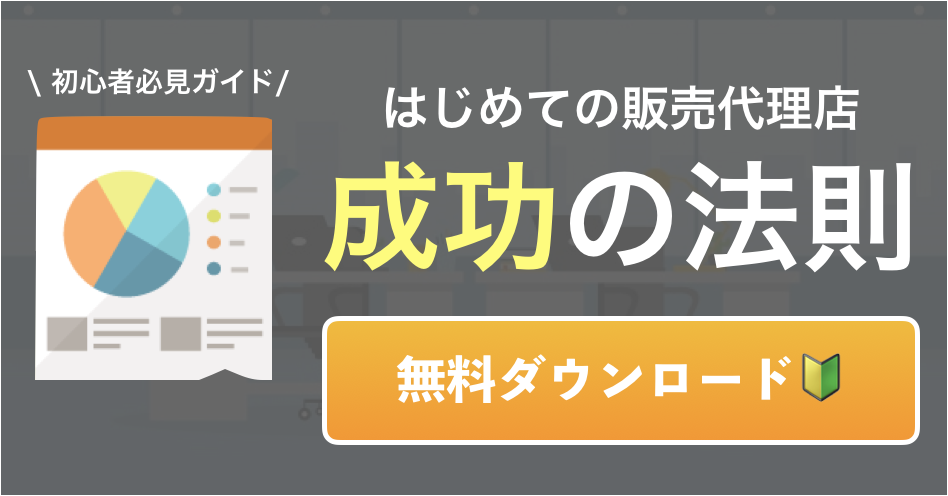個人事業主とは?
個人事業主とは、法人格を持たずに事業を行なっている事業主であり、個人もしくは家族で経営しています。人数に関しては特に決まった制限はありません。基本的には少人数で経営されていることがほとんどです。
最近はフリーランスやのノマドワーカーも増えてきていますが広い意味では彼らも個人事業主ということになります。「事業」という言葉に含まれる意味は「反復して経済活動を行う」というものがあります。したがって、ネット販売を数回した程度では個人事業主ということはありません。
では個人事業主と法人では何が違うのかという点を解説していきます。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人では法的な側面であらゆる点が違います。簡単に個人事業主と法人の違いを説明していきます。
設立時の違い
法人の場合は設立時に様々な手続きが必要です。株式会社の場合は場合は株主の出資を定めたり、定款・登記が必要になります。設立時の費用も20万円程度必要になります。
一方で個人事業主は設立時に「開業届」を提出すれば初期費用がなしで事業を始めることができます。したがって、人数が少なく売上もまだ立っていない段階では個人事業主として活動をし、ある程度の規模になったり人を雇わなくてはいけなくなった段階で法人化をする事業主もいます。一概にどちらがいいいということは言えず、自分の今の状況にあった判断を下す必要があります。
廃業の際の違い
廃業した際にも個人事業主と法人では手続きが変わってきます。個人事業主の場合は廃業届を税務署に提出するだけになります。一方で法人の場合は解散の生産や登記の手続きが必要になります。
株式会社の場合は持分の株をどのように処理するのかなど、ステークホールダーが多い分やるべき手続きも増えてくるのです。
税金に関する違い
個人事業主と法人の一番大きな違いは課税のシステムでしょう。多くの個人事業主が節税のために法人に切り替えています。個人事業主の税制の特徴は累進課税です。個人事業主の課税所得金額は以下の通りです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
この他にも住民税、個人事業税などがかかってきます。売上が小さいうちは個人事業の方が節税になりますが分岐点を越えると法人にした方が課税の面でメリットが大きいのです。
これに対して法人税は売上に関わらず一定30%程度になっています。しかし、赤字でも最低7万円の税金がかかるため、利益が低い時は不利になることもあります。
個人事業主として事業をするメリット
開業するための手続きが簡単
法人は設立にあたって登記を行います、登記に必要なものは定款や会社印など。さらに開業届には添付書類が必要になります。これらの手続きは煩雑なため税理士にお願いしるケースも多いです。
一方で個人事業主の場合は開業にあたって書類や資料は必要ありません。国税庁のホームページから開業届をダウンロードし、記入して郵送で遅れば手続きが完了するので全部で30分程度で終わらせることができます。スピード感を持ってとにかく早く始めたい方にはおすすめです。
設立の費用がかからない
法人設立にあたって株式会社、合同会社など種類によって異なる設立費用がかかります。株式会社の場合は20万円程度かかるのに対して個人事業主は設立費用がかかりません。手続きを税理士に依頼したとしても法人よりも簡略な手続きで済むので費用も抑えられます。
まだ売上が立っておらず、少しでもコストを抑えたいという方にとっては設立費用がかからない個人事業主からスタートするのも良いでしょう。
社会保険の加入義務がない
法人の場合は構成員が社長一人であっても社会保険に入ることが法律で義務付けられています。個人事業主では五人以上常時雇用している場合は社会保険加入の義務が命じられます。まだ、人数が少ない、また家族で経営をしている場合などは個人事業主の方が節税に繋がるでしょう。
赤字の際は課税がかからない
個人事業の場合は年間の収益が赤字の場合は課税がありません。法人の場合はたとえ赤字であったとしても最低七万円の税金がかかります。赤字は最大で三年繰り越すことができるということも覚えておきましょう。
個人事業主として事業をするデメリット
社会的信頼を得づらい
法人にしておくとあらゆる場面で個人事業主よりも信用が得やすいと言えるでしょう。会社間の取引においても法人か個人事業主かで相手に与える印象は全く違います。会社によっては法人としか取引をしないという場合もあるほどです。
また、銀行から融資を受ける時も法人なのか、設立何年なのかというのは非常に重要なポイントです。
良い人材を採用しづらい
求職者の立場から考えてみると法人か個人事業主どちらがいいかというのは一目瞭然でしょう。求職者が求めるものの一つに「安定」というものがあります。組織を大きく見せるという面でも法人化しておくことはメリットが大きいでしょう。
事業を継続させづらい
「法人格」と言われるように創業者とその会社は切り離して考えられます。よって大株主である創業者が退任したとしても取締役に後継者が入ることは容易です。しかし個人事業主の場合、事業と事業主が切り離されていないため事業譲渡に煩雑な手続きが必要になり、事業の継続性が低くなります。
個人事業主はこんな人におすすめ!
早期に事業を拡大するつもりはない
法人にすると収益の大小に関わらず一定の税金を収めなければいけないので個人事業主はまだ収入が小さい場合にはおすすめです。
しかし、今は売上が立っていないが短期間で事業を成長させたいという方には法人をおすすめします。取引をする会社が大きくなるほど個人事業主では相手にされない場合もあるのです。もしも当分は小規模でやっていく場合には個人事業主の方がメリットは大きいでしょう。
事業を起こすにあたって「自分がどこを目指すのか」を明確にして決めると良いでしょう。
黒字化する目処がたていない
先述したように法人格を持つと売上の大きさに関わらず、一定の税金を収めなければいけません。売上規模が小さい時期はこの一定の税金も事業に影響を及ぼすので軌道に乗るまでは個人事業主のままでも良いでしょう。
個人事業主として開業するまでにやるべきこと
個人事業主としてやるべき手続きは以下のようになります。
| 手続き | 窓口 | 期限 | 持ちもの | |
|---|---|---|---|---|
| ①厚生年金から国民年金への切り替え | 市区町村役場 | 退職した日から 14日以内 |
年金手帳、厚生年金等退職の日付が分かるもの、印鑑、免許証などの身分証明書 | |
| ②会社の健康保険から国民健康保健への切り替え | 市区町村役場 | 退職した日から 14日以内 |
健康保険資格喪失書、印鑑、免許証などの身分証明書 | |
| ③個人事業の開業届出書 | 税務署 | 1カ月以内 | 印鑑、免許証などの身分証明書 | |
| ④青色申告承認申請書 | 税務署 | 2カ月以内 | 印鑑、免許証などの身分証明書 |
国民年金・国民保険への切り替え
会社員から個人事業主になるには「健康保険から国民健康保険」「厚生年金から国民年金」に変更手続きを行う必要があります。上記の表にあるように退職してから14日以内に手続きを完了させる必要があります。
開業届の提出する
個人事業の開廃業等届出書、いわゆる開業届を提出する必要があります。事業開始から1ヶ月以内に提出しなければいけないという決まりはあるのですが、実際には提出をしなくても法的に問題になることはありません。ブログで収益をあげている方やプログラマーとして個人で受託をしている人の中にも開業届を出さずに活動している人は実は多いのです。
ただし、銀行口座を開設する際や法人と取引をする際に屋号の記載を求められることもあるのでなるべき早めに開業届を出しておきましょう。
申告承認申請書を提出する
確定申告を青色申告と白色申告があります。青色申告をする場合は、開業後2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告にすると赤字を3年間繰り越せたり、65万円の控除があったりと特典がある代わりに、複式簿記などで帳面付けする必要があります。
その一方で簿記の知識がないと難しい、複式簿記の帳簿を作成するのが面倒というハードルがあります。しかしよほどの理由がない限りは青色申告をしましょう。
個人事業主として収益を伸ばすためには?
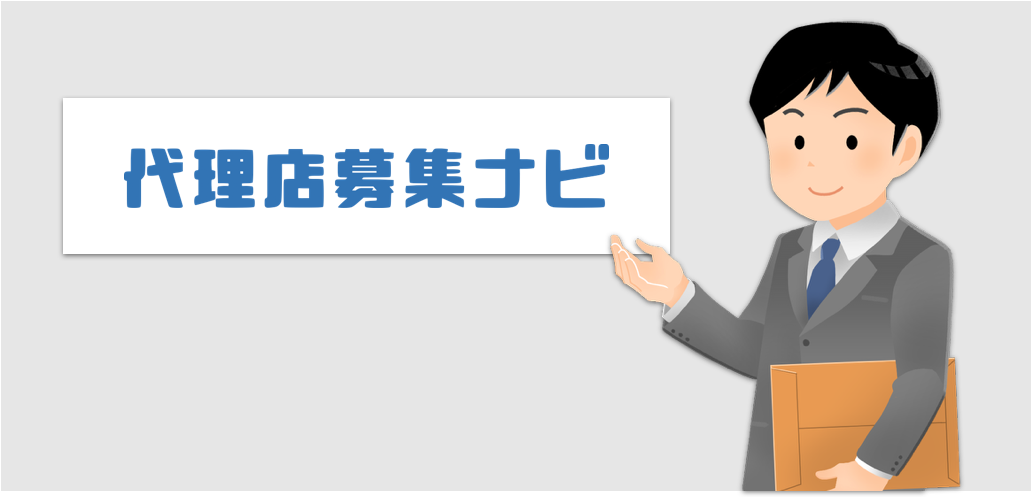
代理店募集ナビとは「独立して個人事業主になりたい」「収益をもっとあげたい」という方に、より好条件の案件を紹介する国内最大の代理店募集サイトです。個人事業主として代理店で大きな収益をあげている方も非常に多く、長年に渡って利用されています。
「独立したいけど、開業するお金が足りない」「どの商材を選んだらいいのかわからない」という悩みを抱える方取り扱える案件を多く掲載しています。